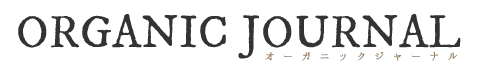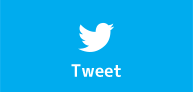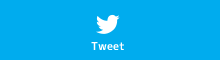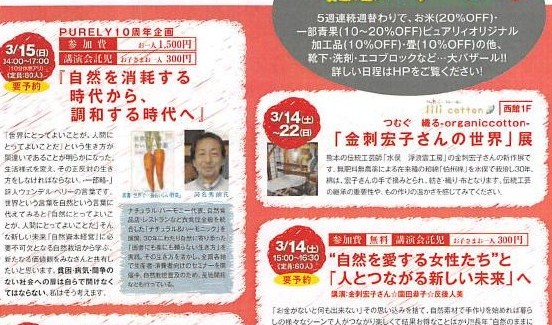『フード・インク』 安いのに安心安全なんてあるわけない
http://yamachanblog.under.moo.jp/?eid=381@yamachanblog
2011.12.08 Thursday [食・生活]
安いものには理由があります。必ずあります。その理由はケースによって様々でしょうが、ふつう消費する側はそこまで考えません。ぼくたちは一円でも安い方がお得だぜと思い、多くの場合それが消費行動の基になります。ただ得したいっていう、それだけです。そういった消費行動が消費する側のデフォルトになっているので、供給する側もそういった消費行動を原理として利益の最適化を企業目的の第一に設定します。
その結果どうなったか。それはぼくらの身の回りをみれば明らかです。地方の地元商店街はどんどん消えて行きました。食材はスーパーマーケットにきれいに陳列され、見た目と値段で購買されます。週末には皆、駐車するまで何十分もかかり、目の血走った人たちでごった返すショッピングモールへと出かけます。ここでは消費もまるでビジネスのように行われます。ぼくら夫婦は出かける度にいつもぐったりです(あまり近づかないようにしてますが)。
内田樹さんによれば、一円でも安ければそちらを買う、というのは「未成熟な消費者」なのだそうです。企業にしてみれば、消費者が未成熟であったほうが販売戦略を立てやすい。ここに双方のニーズが一致します。
さよならアメリカ、さよなら中国 – 内田樹の研究室より
一円でも安ければそちらを買う、というのは、私の定義によれば「未成熟な消費者」ということになる。
「成熟した消費者」とは、パーソナルな、あるいはローカルな基準にもとづいて商品を選好するので、消費動向の予測が立たない消費者のことである。
(中略)
TPPというスキームは前にも書いたとおり、ある種のイデオロギーを伏流させている。
それは「すべての人間は一円でも安いものを買おうとする(安いものが買えるなら、自国の産業が滅びても構わないと思っている)」という人間観である。
かっこの中は表だっては言われないけれど、そういうことである。
現に日本では1960年代から地方の商店街は壊滅の坂道を転げ落ちたが、これは「郊外のスーパーで一円でも安いものが買えるなら、自分の隣の商店がつぶれても構わない」と商店街の人たち自身が思ったせいで起きたことである。
ということは「シャッター商店街」になるのを防ぐ方法はあった、ということである。
「わずかな価格の差であれば、多少割高でも隣の店で買う。その代わり、隣の店の人にはうちの店で買ってもらう」という相互扶助的な消費行動を人々が守れば商店街は守られた。
「それでは花見酒経済ではないか」と言う人がいるだろうが、経済というのは、本質的に「花見酒」なのである。
続きを読む