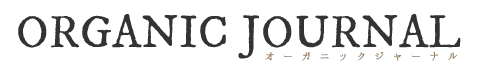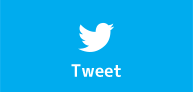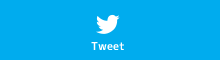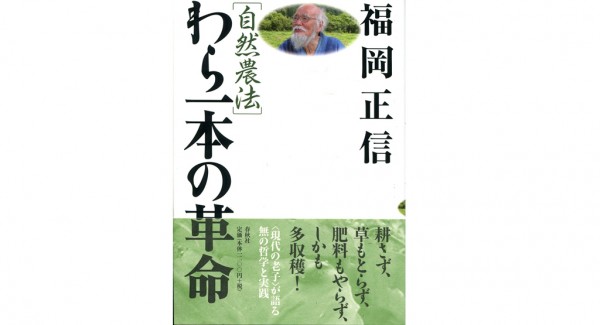【石川県】西田栄喜さん(無農薬野菜・風来店主、通称「源さん」) 日本の“真の食料自給率”は1.5%?
“日本一小さい専業農家”として石川県能美市で少量多品種(年間50種類ほど)の野菜を育て、インターネットを中心に野菜セットを販売2013年より無肥料栽培に挑戦中。
キューバの食糧危機とそれを乗り越えた話。
日本は幸いなことに、有機栽培や自然栽培の分野で世界トップクラスの方々が揃っています。

以前から「食料自給率」という言葉は知っていましたが、漠然と「日本の自給率(39%)って低いんだな」というくらいの認識でした(実はカロリーベースで計算しているのは日本だけ。生産額ベースだと2013年で68%と高くなりますが、それでも先進国中で最低です)。
畜産物に関しては、エサの自給率も按分されます。例えば卵はほぼ国産(95%)なのですが、ニワトリのエサの大半は輸入(エサの自給率が10%)なので、卵の自給率は9%となります。
また食品廃棄も大量に発生しています。その廃棄分のカロリーも分母として含まれるので、廃棄が多いほど低くなります。
ほとんどの肥料・エネルギーを外国に依存
これを野菜や穀物にあてはめてみるとどうでしょうか。
ほとんどの農家が使っている化学肥料、特にリン酸・カリウムはほぼ輸入に頼っているのが現状です。
また大規模農業にはトラクターなど農業機械が必要ですが、その燃料は軽油やガソリンなど外国から輸入した化石燃料です(チッソは国内で製造していますが、その製造に必要なアンモニアを生成するために、莫大なエネルギーが必要となります)。
つまり日本の野菜や穀物は、肥料もエネルギーもすっかり外国に依存しているのです。
日本のエネルギー自給率は約4%。語弊を承知で大ざっぱに言えば、生産にかかるエネルギーを按分した日本の“真の食料自給率”は「39%×4%≒1.5%」なのかもしれません。
現にアメリカはリン鉱石とカリウムを「戦略的物質」と位置づけ、輸出を禁止しています。肥料価格の高騰は日本の農業に多大な影響を与えますし、いつまでも外国から輸入できる保証もありません。
自給率を「国防」という観点から考えるのであれば、食品単体ではなくそれを生み出す肥料やエネルギーなど、トータルに考えなければ意味がないように思います。